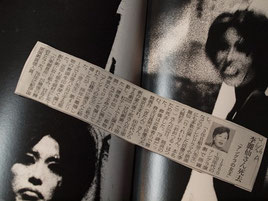
李礼仙が死んだ。
紅テント・状況劇場の看板女優、唐十郎の当時の妻。
状況劇場を初めてみたのは、高校3年生のときだった。そのころ小劇場運動がちょうどピークを迎えていたから、ぎりぎりそれに間に合ったことになる。
演目は「吸血姫」。まだ、麿赤児も四谷シモンも出演していて、彼らはこれを最後に退団してしまう。 ☞
李が紅テントの看板を負うようになったのは、この頃からのようだ。嵐山光三郎との対談で、唐がこう語っている。
“この頃(「吸血姫」)の李はね、一番あぶらが乗りかかったっていうか…。(中略)それまでは李礼仙の代表的なキャラクターってなかなか見つからなくてね。この頃からじゃないかなって僕は思うんだな(CD「状況劇場 劇中歌集」)”。

次作の「二都物語」のいくつかのシーンは今でも鮮烈に覚えている。
タンス(本物である!)を背負ったままさっき不忍池に飛び込んだはずの大久保鷹が、突然びしょ濡れのままふたたびメリーゴーランドの木馬に跨って現れ、軍刀を振り上げる。“だぁー”というダミ声。“あーっ、バッタンバンの木馬だっ!”*と李が叫ぶ。
あるいは、また別のシーン。キャバレーのホステスとして若い客(たしか根津甚八)と絡んでいるところに、ニセの兄 唐十郎が姿を現わす。独特のキラキラした目、あやしげなネチネチした物言い。
唐:ジャスミン、コオトを持って来たよ。
李:あたし、あんたなんか知らないよ。
唐:おコトバだに。雨が降ったら、コオトを持ってくる約束だったぢゃあないか。
李:おニイさん、こんな男の言うこと、聞いちゃダメ! あたし、あんたのユア・ナンバーワン、ユア・ナンバーワンよ!
筋はすっかり忘れてしまい、持っていたはずのシナリオも手元になくなってしまったので、思い違いもありそうだが、なんの脈絡もなく(50年前の!)個々のシーンがよみがえる。甘美な、悪夢のような時空。
「二都物語」は2度みた。不忍池の水上音楽堂から帰るとき、どこかに括りつけられていたポスター(ベニヤ半分大)をかっさらってそのまま山手線(まだ‘国鉄’だった)に乗り込んで帰った。しばらくは自分の部屋に飾ってあったはずだ。

だが、この「二都物語」が紅テントの頂点だったのではないか。
その後、「ベンガルの虎」「唐版 風の又三郎」と
海外にまで足を伸ばしながら、些末な偏執がいつしかとてつもない妄想に拡がっていく唐の作劇が、次第にこじんまりとしたものになっていくようだった。
“まず、戯曲があるのではなく、演出プランがあるのでもなく、バリッとそろった役者体があるべきなのです。(「腰巻お仙」-灰かぐらの由来-)”という唐十郎だったが、麿やシモン、大久保鷹、不破万作といった‘怪優’が徐々に去っていったのは、はたしてそれが状況劇場の変質の原因だったのだろうか。それとも帰結だったのか。どちらともいえるような気がする。
紅テントは、しだいに根津甚八や小林薫といった、のちにテレビでも活躍する役者が中軸となっていくが、以前のような得体の知れないうさん臭く猥雑なエネルギーに充ちた空間はしだいに失われていった。自分の足も遠のいた。その後、この時期の小劇場運動の流れを継いだ‘つかこうへい事務所’や‘夢の遊眠社’などにも興味はまったく持てなかった。磨き上げられたシナリオ、緻密な演出、訓練された役者によって演じられる芝居など、ちっとも面白くなかろう。少なくとも、あの、正気の沙汰とは思えない熱病のような空間を体験してしまったからには。

上演中のライブ音源ではないけれど、紅テントの劇中歌がCDになっている。李礼仙(改名して‘麗仙’になったけれど紅テント時代は‘礼仙’だった)の歌声も。
とりわけ「二都物語」での『ジャスミンの唄』は、今でも口ずさむことができる。
ジャスミン。不滅の女 ―。
柘榴が割れて 口を開ける千のルージュ
今までせっかく眠っていたのに
その口から飛び出した千の鳥
ああ
お前を見たら 誰が忘れよう
乙女の塔がある
悲しみとジャコウの町
馬よ 町よ そんなに赤い渇いた口で
夜はどんな味がするの
李礼仙の霊よ、安かれ。
(唐の著作の装幀は、「吸血姫」四谷シモン、「ジョン・シルバー」横尾忠則、「腰巻お仙」鷲見哲彦、「少女仮面」水木しげる、です。)
* 【後記】“あーっ、バッタンバンの木馬だっ!”は、満州を舞台にした「二都物語」のなかの台詞のわけないですねぇ。たぶん次作「ベンガルの虎」だな。
