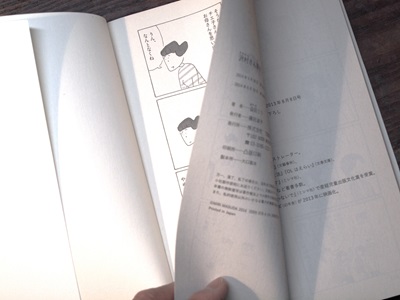益田ミリの「ツユクサナツコの一生」が今年度の‘手塚治虫文化賞(マンガ大賞)’の短編賞に選ばれた。
去年の夏にこのマンガを読んで、それから次々に片っ端らから益田ミリを買い込んで今や72冊(既読50冊、未読21冊、読書中1冊)。これだけ購入した作家は他にはない。 ☞
マンガにしてもエッセイにしても、特段に新たな知見が啓かれたり巻を置く能わずというような展開があるわけでもない。素朴な画はとりわけ達者とも思えないし、内容のほとんどは日常身辺をめぐるささやかな話だ。
作業の区切りにふと一息つくとか、昼寝から目覚めた起き抜けとか、そんなときにちょっと買い置きのスナック菓子を摘まむようにして読む。だが、一度食べはじめたピーナツやポテトチップのようにやめるきっかけを失って、次へ次へとページをめくっている(実のところ間食の習慣は皆無なのでこれはまったくの比喩です)。そして一冊の残りページが少なくなると、読み切ってしまうのを惜しんでぐっとこらえて本を置く。
作業の区切りにふと、と書いたが、むしろ益田ミリを読むために作業を切り上げてしまっているふしもありそうだ。いったいどこがそんなにいいのか。

『お母さんという女』という初期のエッセイ+マンガ。ここでつくづく益田ミリならでは、と恐れ入ったマンガがある。
見開き2ページに16の均等なコマ割り。1コマ目はタイトル。2コマ目に“実家に帰ると、母の隣で寝ることになる”という地の文と“あー”“寝よ”と伸びをする〈ミリ〉。
以下3コマ目から16コマ目まで寝床を並べる母と〈ミリ〉を俯瞰するまったく同一の構図が続く

蒲団を被ったままの母子の会話。
❸ ミ:おやすみー ❹ (沈黙) ❺ 母:お母さんなぁ ❻ 母:カラオケがあって、ホンマによかった思うねん ❼ 母:唄っているとなんかこう ❽ 母:心がスーっとするってゆうか ➒ 母:スッキリするねん ❿ (沈黙-半ば寝入りかけている〈ミリ〉- ⓫ ミ:よかったなあ ⓬ 母:ちょっとテープ聴きながら寝るわ ⓭ 母:むずかしいねん、この曲 ⓮ (沈黙) ⓯ 母:アンタにもろた電池 充電するの便利やわ ⓰ ミ:よかったなあ
― でお終い。オチも展開もなし。小津安二郎だってこれほどのなんてこともないシーンは描かなかったぞ。しかしなんともいわく言い難い味ではないか。
(なおこの作品は2004年に文庫書下ろしとして出版されたのち、マンガを全て描き直し新たな書下ろしも加えた単行本として2009年に上梓された。『すーちゃん』シリーズの好評を踏まえて描き直されたものか。現在 刊行されているのは文庫本だが、マンガの出来ばえは断然 単行本の方がいい。)

『すーちゃん』シリーズのなかのシーン。シリーズ(目下)最終巻の『わたしを支えるもの すーちゃんの人生(2019)』の終盤。ほのかな好意を持つ土田さんとのデートから帰宅したすーちゃんの独り言。やはり見開き16コマ。
❶ (夜景) ❷ (仰向けで天井を見つめるすーちゃん) ❸ つないだよ ❹ 手 ❺ 人間、手くらいつなぐか ❻ (体を起こして) いや いや いや / つながねーな ❼ (沈黙) ❽ ‘はー’➒ (膝を抱えて)‘ふー’❿ (沈黙) ⓫ (沈黙) ⓬ 手、かー ⓭ ‘ふー’⓮ (顔をうずめて)手とか / つなぎますか ⓯ あ、ハイ ⓰ あ、ハイ / て、
この一話はここでふつりと終わる。土田さんとすーちゃんとの関係はその後なんの進展も示されないままこの『わたしを支えるもの』の巻も閉じられる。人生は予定調和するドラマではないのだ。
(『すーちゃん』シリーズは、ショートストーリーの連作ながら雑誌等での連載ではなく、単行本書き下ろしなので、この続編が描かれるのかは不明である。)

益田ミリが〈益田ミリ〉になるきっかけになったと思われるエッセイがある。
『47都道府県 女ひとりで行ってみよう(2008)』
2002~06年にわたって毎月ひとつづつ全国を旅する。ウェブで連載するだけで出版のあてもないまま、“なにかを学ぶ、などにはこだわらない「ただ行ってみるだけ」の旅。/無駄だったかどうかは、旅が終わってからわかるんだろう。(p3)”
こんなふうにスタートした旅は観光名所やイベントなどの情報ガイドとしてはほとんど役に立たない。自分に課した義務のようにして行くから、時に“はっきりいって、もう飽きている。(略) 別に誰も楽しみにしていないだろうし、中止してもいい気がする。(p24)”とか“もうひとり旅なんかしたくない。/こんなことやっていてなんになるわけ?(略) リタイアしようかとも思ったが、せっかく毎月欠かさず続けてきたんだからという思いもあり…(p150)”などという泣き言も出る。
とりあえず目星らしきものをつけて旅にでかけるのだが、ガイドブックを見て日帰り温泉に向かうものの辿りつけずに諦めるはめになったり₍p118 静岡県₎、うろ覚えのフェスティバルに心弾ませて出かけたらすでに会期は終了していたり₍p146 長崎県₎。しかし‘珍道中的なユーモラスな読み物’といった線を狙ったというわけでもないのだ。(アマゾンのレビューには“ネガティブなことばかり”という批判も少なからず見られる。)
では、出版のあてもないままこの旅とそれを書き記すことを自らに課した目的はいったいなんだったか。
益田は“6年ほど大阪でOLをしていたという₍『OLはえらい(2001)』あとがき₎。その経験はさまざまな作品にも反映されている。察するに、そこそこそつなく仕事をこなし上司や同僚とも良好な関係をつくっていたようだ。東京でイラストレーターになるといって退職する日のことを次のように記している。
送別品に絵の具をもらった。文房具ももらった。最後の日、生まれて初めて胴上げをしてもらった。家に帰ってから、一人でわんわんと泣いた。₍『OLはえらい』p186₎
しかし会社勤めの社会人である以上、当然に屈託もある。『OLはえらい』の4コママンガには次のようなシーンもある。
“あ、部長 さっきはごちそうさまでした”(“おー”)“またさそって下さいね”“おー またなー”“楽しみにしてますー”《こういう自分が時々すごくイヤになる “マジで”》(p68)
また、さらに後年、『沢村さん家のこんな生活(2014)』には、会社勤めの主人公と同僚たちが次のようなガールズトークを交わす。
“正直、ご機嫌とるのは苦でもないのよ ご機嫌取ってる自分を周囲に見られるのがイヤなの”(p107)
会社に限らず、世間を渡っていれば、様々な思惑・忖度・見栄・世間体・同調圧力などに囚われながら生きていくことになる。自意識も他者があってこそ生じる。
益田ミリが『47都道府県 …』で無意識のうちにやろうとしたのは、強引に未知の場に自分を放り出すことによって、このような諸々の囚われを、消し去ることはできなくとも、せめて意識化して素(す)の自分を取り戻すことではなかったか。そうでなければ、これから作家としてやっていくことはできない ― そう本能的に感じたのではないか。
そこで、この旅の中で彼女は情けない自分にたびたび向き合うことになる。
新鮮な魚がたっぷりのった「海鮮丼」が有名と聞き、つい市場の中にある海鮮丼の店に入ってしまった。ああ、いつになったら私は「名物」の呪縛から解放されるのだろうか。(略) わたしは魚貝類が苦手なので、普段からほとんど口にしない。(略) 残しては失礼というより、残したことで「味がわかってない奴」とバカにされそうで嫌なのかもしれない。(略) わたしは食べ切れずに、店の人が見てない隙にハンカチに包んでカバンに隠した。(p47-8 石川県)
ひとり旅の女が、淋しく見えないようにするにはどうすればいいのだろう? ひとり旅は淋しくなくなりつつあるけれど、淋しく見られることことには抵抗が……。(p78 鹿児島県)
今年になって、わたしはつくづく自分を嫌になることが多くて、そのうちのひとつが、社交辞令なところである。今度またご飯しましょうね、とか… (略) でもいつもそのまま何もしないでいる自分に飽き飽きしてきたのである。(略) これから柔軟になっていければいいなぁ、などと願う春なのであった。(略) 追記・この旅から4年が過ぎたが、やっぱり柔軟になれなかった……。本当はなりたくないのかも。(p89 山梨県)
「いつも食べに行く店で、どんどん友達が増えちゃって!」などというオープンな生活スタイルなど、絶対に考えられない。知らない客同士がしゃべるなんて、想像しただけで疲れる……。嫌。うらやましくない。(p154 群馬県)
熱心な金魚好きの人たちが金魚を買いにきている中、なぜか観光客ふうの女がひとり紛れ込んでいる感じ……。早く帰りたいと思うものの、タクシーで乗りつけてきたくせに、すぐ帰るのも不自然じゃない? というもののいつもの自意識過剰のせいで、できるだけ熱心に金魚を見てまわるわたし。(p174 奈良県)
33歳から37歳までの4年間で47都道府県の旅を終え、その2年後に出版された本の‘あとがき’で益田ミリは次のように記す。
旅をはじめたばかりの頃は、名物を食べなければという焦りとか、しゃべる相手のいない淋しさがのしかかっていたけれど、回数を重ねていくうちに少しずつ気軽になった。惣菜を買ってホテルでひっそり食べるのも、いつのまにか抵抗がなくなっていた。旅先での「人とのふれあい」も、まったくと言っていいほどなかった。ふれあおうとする努力もしていなかった……。
そして“わたしは、この、ゆる~いひとり旅で何かを得たのだろうか?”と自問しつつ、次のように記す。
ちょっと大袈裟に言うなら、「人生は一回しかない」っていうことをひしひしと感じた4年間でもあった。/わたしは、旅先でよく道に迷った。地図を片手にしょっちゅう路地裏をさまよっていた。そんなときに、民家の庭先で洗濯物を干しているおばさんの前を通り過ぎると、ああ、この人には、もう一生会うこともないんだなって切なくなる。あのおじさんも、あの女子高生とも会うことがない、へんぴな場所に行けばいくほど、その気持ちが強くなり、さよなら、さよならって無性に悲しかった。だけど、そういう気持ちを味わうのは、わたしにとって良かったことのように思うのだった。(p246)
こうして作家・益田ミリが誕生する。『すーちゃん(2006)』が上梓されたのは、この旅の最終盤である。
『47都道府県 …』は、文庫化されて、なんと57刷のロングセラーになっているそうである。

手塚賞を受賞した『ツユクサナツコの一生』は、“すべての読者がこの本のラスト近くでびっくりさせられることでしょう(23.8/12 中条省平「マンガ時評」)”とか“終盤は衝撃の展開(24.4/22 朝日新聞)”などと書かれる。
確かにこんな“衝撃の展開”は従来の益田作品にはまず見られなかった。
でも、この展開はこれまでのマンガ・エッセイにも通奏低音のように響いていたものだ。構成の妙も含め、益田ミリの新たな代表作である。
おまけ

エッセイのイラストに描かれる本人の画姿を真似して描いてみました。
・右上は2008年頃~。独自のスタイルを確立しつつも世間との距離を測りかねている表情。
・左上が2015年頃~現在。もはや自分の立ち位置というものが腹に落ちている。
・下はマンガ家スタートの頃。まだまだ類型的ですね。
(益田ミリはイラストレーターを志したこともあって、初期には現在からは想像しがたいスタイリッシュなイラストも描いている。 ☛『こんな気持ちが恋だった(2002)』,『昨日うまれた切ない恋は(2004)』)
大阪人らしいサービス精神。“タコ焼き1コ、おまけしとったで”ってな感じ?
・左:『沢村さん家のこんな毎日(2014)』の奥付の裏ページに付け加えられた‘特別番外編’のマンガ。同時期に連載中の『泣き虫チエ子さん』の主人公が愛読書として『沢村さん家…』をさりげなく宣伝する。なお、『沢村さん家…』は文藝春秋社、『泣き虫チエ子さん』は集英社である。
・中:『泣き虫チエ子さん2(2013)』の巻末の出版広告。集英社以外の、幻冬舎、講談社、飛鳥新社、ポプラ社の著作が紹介される。著者のプロフィールのなかで紹介されることはあっても、このように画像とともに堂々と紹介されることは見たことがない。編集者とよくよくの良好な関係がなければありえないのではなかろうか。
右:『僕の姉ちゃん的生活(2020)』の巻末。4ページにわたって描き下ろしが加えられている。本というものは、全紙が裁断されて8ないし16ページ分になった‘折り丁’が重なって綴じられ製本される。したがって、内容量によってはページが余ってしまうということが起こりうる。その場合、白紙のままにするか、それでなければ自社の出版物の広告ページにする。益田はそれを嫌ってぎりぎりのページまで自作の描き下ろしを加えたのだろう。益田ミリの著作で、巻末に他者の著作紹介や白紙が現れることはまずない。尻尾までアンコが詰められた鯛焼きのようなものか。